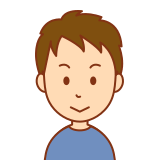
飲食店って将来性あるのかな?
人手不足って言われてるけどそれってこの先はあまり期待出来ないってことなのかな?
飲食店は昔から人気のある仕事ですが、
「この先も働き続けられるのか」
「将来性はあるのか」
と不安に感じる方も少なくありません。
近年は人手不足や労働環境の厳しさが問題視される一方で、テクノロジーの導入や新しい業態の広がりによってチャンスも増えています。
この記事では、飲食店の将来性について現状と今後の展望をわかりやすく解説していきます。
この記事で分かることは以下の通りです。
わたくし、かーりーは、20年以上、様々な飲食店で働き、その後、他の職種へ転職しました。
その経験や知識をもとに今回のお悩みに応えていきます。
飲食店の将来性とは?現状と未来を俯瞰する

飲食店の将来性は「厳しい環境の中でも成長のチャンスがある」というのが実情です。
市場の拡大や観光需要の回復といった追い風がある一方で、人手不足やコスト上昇といった課題も避けられません。
つまり、飲食店の未来は明るい部分と厳しい部分が混在している状態です。
ここからは、外食産業の市場規模、コロナ禍からの回復、そして社会背景の変化について詳しく見ていきます。
外食産業の市場規模と近年の動向
外食産業は国内で20兆円規模を超える大きなマーケットです。
家計支出の中でも食事関連の割合は依然として高いままです。
特に近年は共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化から「外食・中食の利用回数」が増えています。
ただし、業態ごとの明暗ははっきりしていて、ファストフードやテイクアウト型は成長傾向。
居酒屋業態は厳しい状況が続いています。
数字が示す通り、需要の形が変わりつつあることが将来性を語るうえで重要なポイントです。
コロナ禍からの回復とインバウンド需要
コロナ禍で外食産業は大きな打撃を受けましたが、2023年以降は観光需要の回復に支えられて明るい兆しが出ています。
特に外国人観光客の増加によって、都市部や観光地の飲食店は売上を伸ばしやすい状況です。
一方で、全ての飲食店が一律に回復しているわけではなく、立地や業態によって差があります。
今後の将来性を考えるなら、インバウンドを取り込める体制を整えるかどうかが重要な分かれ道になるといえます。
社会背景(人口減少・働き方改革・消費者行動の変化)
日本全体で人口が減少し高齢化が進む中、飲食店の将来性にも直接的な影響が出ています。
働き方改革により労働時間の規制が強まり、従業員の確保が難しくなっているのも事実です。
また、消費者の行動は「安さ重視」から「体験や価値重視」へと変化しつつあります。
この背景を理解せずに経営を続けると競争に取り残されてしまいます。
逆に言えば、社会変化を踏まえて柔軟に対応できる店舗は将来性を伸ばせるチャンスを持っています。
飲食店の将来性を示すデータ

飲食店の将来性を考えるとき、感覚や印象だけで判断してしまうと危険です。
実際の数字や統計を見ることで、現実の厳しさと成功の可能性を冷静に把握できます。
ここでは、飲食店の生存率や廃業率、さらに成功している店舗の共通点をデータを交えて解説します。
飲食店が10年続く確率
飲食店が10年以上存続する確率は全体のわずか1割程度といわれています。
ということは、多くの店舗が数年で撤退しているわけです。
この数字だけ見ると将来性は厳しく感じますが、成功して長く続く店舗も確実に存在しています。
つまり「飲食店は続かない」と決めつけるのではなく、長く続けるためにどんな工夫が必要かを考えることが重要です。
廃業率や倒産件数の実情
飲食店の廃業率は他の業種と比べても高く、特に開業から数年以内に閉店するケースが目立ちます。
人件費や仕入れコストが変動しやすく、景気や社会情勢の影響を受けやすい業界だからです。
ただ、全体的な倒産件数を見ると、中小規模が大半を占めているのも特徴です。
裏を返せば、資金力や運営の工夫次第で生き残れる余地があるともいえます。
成功率の高い飲食店の特徴
長く続く飲食店にはいくつか共通点があります。
たとえば、
- 立地とコンセプトの一貫性
- 固定客をしっかりつかんでいる
- 時代の変化に合わせてメニューやサービスを柔軟に変えている
などです。
僕の経験からも、常連客に支えられているお店は景気の波に左右されにくいと感じます。
成功率が高い店舗は、単に料理がおいしいだけではなく、経営の視点を持って改善を続けているのが特徴です。
今後の飲食店を左右するトレンド

飲食店の将来性を考えるうえで、これからどんなトレンドが定着していくのかを知ることは欠かせません。
食のニーズは時代とともに変化しており、その波に乗れるかどうかが生き残りの分かれ道になります。
ここでは、テイクアウト需要や健康志向、テクノロジーの進化など、今後の方向性を左右する要素を整理してみましょう。
テイクアウト・デリバリー需要の定着
コロナ禍をきっかけに一気に広がったテイクアウトやデリバリーは、一過性ではなく生活の一部として定着しました。
共働き世帯や一人暮らしの増加により、「外食と自炊の中間」という選択肢が重視されています。
将来性を高めたい飲食店は、専用メニューの開発やアプリ連携など、持ち帰りや配達に適した仕組みを整えることが求められます。
健康志向・サステナブルな飲食業態
健康や環境への意識が高まる中、低カロリーやオーガニック食材を取り入れた飲食店の注目度が上がっています。
特に若い世代を中心に、
「食べること=体と地球への投資」
という考え方が広がっています。
プラごみ削減やフードロス対策も話題となり、サステナブルな取り組みを打ち出す店舗は共感を得やすいです。
こうした価値観の変化を見据えることが、将来性を強めるポイントになります。
DX・テクノロジーが生む新しい飲食モデル
注文や決済をアプリで完結させる仕組みや、ロボットによる調理補助など、飲食業界でもDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいます。
人手不足の対策だけでなく、顧客データを分析してサービス改善につなげられるのも魅力です。
最新技術を取り入れることで、効率化と顧客満足度の両立を実現できる店舗が増えています。
テクノロジーに柔軟な姿勢を持つかどうかで、将来性は大きく変わります。
これから伸びると予想される業種・業態
今後成長が期待されるのは、カジュアルな価格帯で提供できるファストフード型や、健康意識に対応したカフェ業態です。
さらに、専門性の高い専門店や地域の特色を生かした飲食店も支持を集めやすい傾向があります。
僕の経験からも、強みを明確にした業態は常連客をつかみやすく、競争に強いと感じます。
将来性を考えるなら、
「誰に何を届ける店なのか」
を明確にすることが成功への近道です。
飲食店の将来性を阻む課題

飲食店の未来には明るい可能性がある一方で、避けて通れない課題も存在します。
人手不足やコスト上昇、厳しい労働環境など、経営を圧迫する要因は年々強まっています。
こうした問題を正しく理解しなければ、せっかくのチャンスも活かせません。
ここでは、飲食店の将来性を阻む主なリスクについて整理してみます。
深刻化する人手不足と2030年問題
飲食業界では慢性的な人手不足が続いており、特に若い世代の応募が減っているのが大きな課題です。
さらに、2030年には日本全体で労働人口が大幅に減少すると予測されています。
人材が確保できなければ営業時間を短縮せざるを得ず、売上減にも直結します。
人手不足は単なる現場の問題ではなく、将来性を左右する経営課題といえるでしょう。
食材費・光熱費などコスト上昇の影響
原材料の価格や光熱費が高騰し、飲食店の利益を圧迫しています。
特に中小規模の店舗は仕入れ価格の上昇をそのまま転嫁できず、経営が厳しくなりやすいです。
利益率が低下すれば、新しい取り組みに投資する余裕もなくなります。
将来性を考えると、コスト管理の工夫や価格戦略の見直しが欠かせません。
労働環境の厳しさと離職率の高さ
飲食業は、
「長時間労働」
「休みが少ない」
といったイメージが根強く、実際に離職率も高い傾向があります。
働き手が定着しないことで、教育コストが増え、サービスの質が安定しないという悪循環に陥るケースもあります。
改善が進まなければ、優秀な人材が集まりにくくなり、将来性に大きな影響を与えるでしょう。
経営者が直面する資金調達・競争リスク
新規参入がしやすい業界だからこそ競争は激しく、資金繰りに苦しむ経営者は少なくありません。
銀行融資の審査も年々厳しくなっており、安定した資金調達ができるかどうかが経営を左右します。
さらに、大手チェーンや資本力のある企業と競合する場合、個人店は差別化戦略を徹底しなければ埋もれてしまいます。
飲食店の将来性を高めるには、この資金と競争のリスクを冷静に見極める必要があります。
飲食店の将来性を高める経営戦略

将来性を持つ飲食店に共通するのは、時代の変化に合わせて柔軟に戦略を変えている点です。
人手不足やコスト上昇といった課題に直面しながらも、工夫次第で持続的に成長できる可能性があります。
ここでは、飲食店の未来を切り開くために押さえておきたい具体的な経営戦略について紹介します。
DX導入による業務効率化と人手不足対策
人手不足を補う方法のひとつがDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入です。
セルフオーダーやキャッシュレス決済、在庫管理システムを導入すれば、少ない人数でも効率的に店舗を回せます。
僕の経験でも、ITツールを活用する店舗はスタッフの負担が減り、サービスの質が安定しやすいと感じます。
効率化は単なる省力化ではなく、顧客満足度を高める重要な要素です。
外国人材や多様な働き手の活用
人手不足の解決には、外国人材やシニア、主婦層など多様な人材の活用がカギになります。
言語や文化の違いがあるものの、教育体制を整えれば戦力として大きな力を発揮します。
むしろ、外国人スタッフがいることで海外からの観光客への対応力が高まり、店の魅力が増すこともあります。
幅広い人材が安心して働ける環境づくりが、将来性を支える基盤になります。
固定客(ファン)を育てる仕組みづくり
飲食店にとって安定した収益を支えるのは固定客の存在です。
SNSでの情報発信やポイントカード、会員制度などを通じてファンを増やす仕組みを持つことが重要です。
僕の知っている店舗でも、常連客との信頼関係が強い店ほど景気に左右されにくい傾向があります。
新規客を集めるだけでなく、長く通いたくなる仕掛けを意識することで、将来性がぐっと高まります。
資金調達・経営改善の実践方法
飲食店の経営を続けるには、資金繰りを安定させることが欠かせません。
銀行融資だけでなく、クラウドファンディングや補助金制度を活用する道もあります。
さらに、売上分析やコスト管理を徹底して経営の無駄を減らすことも必要です。
資金と経営改善の両輪を回すことで、次の投資に挑戦できる余裕が生まれ、将来性を広げることができます。
飲食店の将来性とキャリア形成の考え方

飲食店の将来性は経営者だけでなく、働く人のキャリアにも深く関わります。
業界の変化にどう対応するかによって、成長のチャンスをつかめるかどうかが変わります。
ここからは、飲食業界でキャリアを築くうえで考えるべきポイントを整理していきます。
今後も成長できるスキルやキャリア戦略
飲食業界で長く活躍するためには、調理や接客だけでなく、マネジメントやマーケティングのスキルも身につけることが有効です。
たとえば、SNSを使った集客やスタッフ育成は、将来どんな業態でも役立ちます。
キャリア戦略としては「現場力+経営視点」を意識することが成長のカギになります。
飲食業界で働き続けるメリット・リスク
飲食業界には、
「人と直接つながれるやりがい」
「自分の努力が形になる喜び」
といった大きな魅力があります。
その一方で、労働環境の厳しさや景気の影響を受けやすいリスクも存在します。
働き続けるメリットとデメリットを理解したうえで、自分に合ったキャリアを選ぶことが大切です。
独立・転職・投資を考える際の判断基準
飲食業界でキャリアを積んだ先には、独立や転職、投資という選択肢があります。
判断基準になるのは、自分の強みやライフスタイル、リスク許容度です。
独立は自由度が高い反面、経営リスクが伴います。
転職は安定を得やすく、投資は資本力が求められる選択です。
それぞれの特徴を理解したうえで、最適な道を選ぶことが将来性につながります。
経営者・従業員・投資家それぞれの視点から見る将来性
飲食店の将来性は立場によって見え方が変わります。
経営者は収益性や持続可能性を重視し、従業員は働きやすさや成長環境を重視します。
投資家にとっては市場動向や収益モデルが重要なポイントです。
複数の視点から飲食店の未来を考えることで、偏りのない判断ができます。
飲食店の将来性はリスクとチャンスの両面を見極める

飲食店の将来性は「厳しい」と言われることもありますが、実際にはリスクとチャンスが表裏一体となっています。
人手不足やコスト上昇といった課題がある一方で、DXや新しい業態の台頭など希望の芽も確かに存在します。
大切なのは、課題を直視しつつも変化に柔軟に対応していく姿勢です。
経営者・従業員・投資家それぞれが冷静に判断し、成長できる分野に力を注ぐことで、飲食店の未来はまだまだ広がっていきます。

