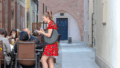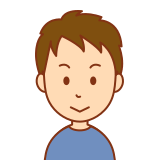
飲食店は休みが中々ないと言われるけど実際どうなんだろう?
なぜ休みがないと言われるんだろう?
「飲食店は休みがない」と耳にすることは多いですよね。
実際、長時間労働や人手不足によって休日が取りづらい職場も少なくありません。
僕自身も飲食業で働いていたときに「休めないつらさ」を何度も経験しました。
この記事では、飲食店の休日事情の実態や休みが取れない理由、改善のためにできる工夫などををわかりやすく解説します。
この記事で分かることは以下の通りです。
わたくし、かーりーは、20年以上、様々な飲食店で働き、その後、他の職種へ転職しました。
その経験や知識をもとに今回のお悩みに応えていきます。
飲食店はなぜ「休みない」と言われるのか

飲食店は「休みがない」とよく言われます。
その理由は、営業時間の長さや人手不足、さらに正社員や店長に負担が集中する構造があるからです。
僕自身、飲食業で働いていたとき、朝から深夜まで働くことが多く、休みが取りにくいと実感していました。
こうした環境は業界特有のものでもあります。
ここからは、具体的にどんな要因があるのかを掘り下げて説明します。
営業時間の長さ
飲食店が休みを取りにくい大きな理由のひとつは、営業時間の長さです。
営業時間が長く、朝の仕込みから夜遅い閉店作業まで、1日中お店を回す必要があります。
結果、勤務時間が長くなり、休憩や休日を確保しにくくなるのです。
僕の経験でも、ランチとディナーの両方を担当する日は休憩が短く、まるで1日がお店に取られてしまう感覚でした。
お客様にとって便利な分、スタッフの労働時間は犠牲になりやすいという構造があります。
人手不足によるシフト調整の難しさ
飲食店が「休めない」と言われるもう一つの理由は、人手不足です。
アルバイトやパートが欠けると、正社員が穴埋めをするしかなくなります。
結果としてシフトの自由度がなくなり、休みが減ってしまうのです。
実際に僕の職場でも、急な欠勤があると店長や社員が代わりに入ることが当たり前でした。
シフトがうまく回らないと、せっかくの休日が急に仕事に変わることもあります。
こうした状況が「休みがない」と言われる背景です。
店長や正社員に負担が集中する構造
飲食店では、店長や正社員に責任が集中します。
売上管理や人材育成に加え、現場に立って調理や接客をすることも多いです。
そのため、休みを取りたくても実際には難しい状況になりがちです。
僕の知っている店長も、休日でも電話対応や仕入れで店に来ていました。
役割が広すぎて「休んでいるのに休めていない」感覚になるのです。
結果として、飲食店全体が「休みがない業界」と見られてしまいます。
飲食店の休みの実態を徹底解説|年間休日・定休日・長期休暇

「飲食店は休みがない」と言われますが、実際には店舗や雇用形態によって違いがあります。
年間休日の平均や定休日の有無、さらにお盆や正月といった繁忙期の扱いは店によって大きく変わります。
僕が働いていた時も、土日や大型連休はほぼ出勤でしたが、平日にしっかり休めるケースもありました。
ここでは、飲食店の休みの実態をわかりやすく整理して解説します。
飲食店の平均年間休日数
飲食店の年間休日は、他業界と比べて少なめです。
一般企業であれば年間120日前後が多いですが、飲食業では100日未満のケースも珍しくありません。
求人票に「月6日休み」と書かれていると、年間で72日しかない計算になります。
僕も働いていた時期は、休みが月6~7日程度で、まとまった休日はほとんどありませんでした。
数字で見てみると、休みが少ないと感じるのも納得できるでしょう。
お盆・正月・GWなど繁忙期・長期休暇の事情
一般企業では長期休暇となるお盆や正月、ゴールデンウィークですが、飲食店にとっては繁忙期です。
むしろ休みが取りづらく、人手が必要になります。
僕の経験でも、年末年始はフル出勤が当たり前で、連休を楽しむ友人をうらやましく思ったことがあります。
繁忙期はかき入れ時なので、休みたい人にとってはつらいですが、その分売上ややりがいを感じられる時期でもあります。
定休日や中休みの種類と実態
飲食店の中には「毎週月曜定休」や「ランチとディナーの間は中休み」といった仕組みを取っているところもあります。
ただし、定休日があっても仕込みや発注で社員が出勤する場合があります。
僕も以前、店が休みでも仕入れや掃除で半日だけ出ることがよくありました。
中休みも実際には休憩というより雑務に追われることが多く、完全に休めるわけではないのが実情です。
土日休みは取れる?平日休みとの違い
飲食店では土日が繁忙日のため、土日に休めるケースはかなり限られます。
その代わり、平日に休みを取れることが多く、役所の手続きや病院に行きやすいといったメリットがあります。
僕自身も平日休みを利用して混雑を避けて出かけることができ、これは飲食業ならではの良い点だと感じていました。
土日休みを希望する場合は、企業や店舗の方針を事前に確認することが大切です。
飲食店社員・店長が休めない背景とは

飲食店で「休みがない」と言われるのは、現場の仕組みに深く関係しています。
シフト管理の難しさや、人手不足、さらには業界特有の文化が重なっているのです。
ここでは、社員や店長がなぜ休みにくいのか、その具体的な背景を解説します。
シフト管理や欠員対応の課題
結論から言うと、シフト管理は飲食店の大きな悩みの種です。
理由は、人員が少ない中で急な欠勤や体調不良に対応する必要があるからです。
例えば、アルバイトが休んだ場合、その穴を埋めるのは店長や社員になるケースが多いです。
結果的に休みが取りづらくなり、長時間勤務につながってしまいます。
こうした構造は多くの飲食店で共通しています。
「365日営業」の文化が根強い理由
飲食店が「休みなし」と言われる理由の一つは、365日営業を続ける店舗が多いからです。
特にチェーン店では「いつでも開いている安心感」を売りにしているため、簡単に休業できません。
実際、正月やお盆でも営業している店舗は珍しくなく、そのしわ寄せは社員や店長に集中します。
この文化が根強い限り、完全な休みを取りにくいのが現実です。
人材不足で負担が集中する現状
最大の背景はやはり人材不足です。
飲食業界は慢性的に人手が足りず、特に正社員が不足しています。
その結果、一人の社員に複数の業務が集中し、休日返上で対応せざるを得ない状況が生まれます。
僕も現場で経験しましたが、欠員が出れば自然と自分の休みがなくなる。
こうした状況が業界全体で広がっているのです。
飲食店で休みを確保するために知っておくべき求人情報

飲食業でも休みをしっかり確保できるかは、求人情報の見方次第です。
表現の違いや制度の有無を理解することで、実際の働き方を見極められます。
ここでは求人票で特に注目すべきポイントを紹介します。
「完全週休2日制」と「週休2日制」の違い
結論から言うと、この2つは大きく意味が異なります。
「完全週休2日制」は毎週必ず2日休める制度です。
一方「週休2日制」は月に1回でも2日休みがあればOKという緩い基準です。
そのため、「週休2日制」と書かれていても実際は月6日程度しか休めない場合もあります。
求人票を見るときには必ず「完全」が付いているか確認しましょう。
「月8日休み」とは実際どのくらい休めるのか
月8日休みは飲食業界でよく使われる表現です。
計算すると年間休日は約96日となり、一般企業の平均(120日程度)より少なめです。
しかも繁忙期は8日休めないケースもあり、実態は店舗によって差があります。
ただし、業界の中では比較的休みが多い部類なので、労働環境を重視するなら目安にするとよいでしょう。
土日休み・連休が取れる飲食店の特徴
土日休みや連休を取りやすいのは、カフェや企業内食堂、学校給食など営業時間が限られている業態です。
反対に、居酒屋やファミレスなど夜営業が中心の店舗は土日が繁忙日になるため休みにくいです。
求人票を見るときに「土日祝休み」と書かれていれば、比較的プライベートと両立しやすい環境だと考えられます。
求人票で確認すべき休暇制度のチェックポイント
休みを確保するためには、求人票の休暇制度を細かく見ることが大切です。
有給休暇の取得率、長期休暇の有無、特別休暇制度などが記載されているかを確認しましょう。
また「年間休日○日」と明記してあるかどうかも重要です。
数字で示されていれば、実際の休みがイメージしやすく、働く環境を比較する判断材料になります。
飲食店でも休みを確保する方法と事例

飲食店は、
「休めない」
「プライベートの時間が取れない」
というイメージを持たれがちですが、実際には工夫次第でしっかりと休みを確保することが可能です。
近年では、働き方改革の流れもあり、飲食業界全体で労働環境を改善しようという動きが進んでいます。
ここでは、具体的にどのようにして休みを確保できるのか、そして実際の事例について解説します。
シフト管理の改善による休暇確保
飲食店で休みを増やすには、まずシフト管理の工夫が欠かせません。
- 1人に負担が集中しないよう、スタッフ同士でシフト交換しやすい仕組みをつくる
- 週ごとに希望休を出せる制度を取り入れる
- シフト作成をアプリやシステム化して効率化する
これらを徹底するだけで「休めない」という不満は大幅に減ります。
休みが取りやすい職場を選ぶポイント
転職時には以下の点をチェックすると、休暇の取りやすさを見極めやすいです。
- 求人票に「完全週休2日」や「年間休日◯日」と明記されているか
- 店舗の営業時間が長すぎないか(深夜営業がない方が休みやすい)
- 人員体制が十分にあるか(慢性的な人手不足の店は要注意)
- 面接時に「休み希望はどの程度反映されますか?」と質問してみる

休暇制度や働き方改革を進める企業の事例
飲食業界の中でも、社員の定着率向上や人材確保のために休暇制度を積極的に取り入れる企業が増えてきています。
年間休日を大幅に増やす企業や、有給休暇の取得率を上げる取り組みを行う大手チェーンもあり、
「飲食店だから休めない」
という常識は変わりつつあります。
これらの事例から分かるように、職場環境の改善に取り組む企業を選ぶことが、ワークライフバランスを実現する大きなポイントとなるでしょう。
年間休日120日を導入した企業の例
近年は、飲食業界でも「年間休日120日以上」を掲げる企業が増えてきています。
従来の「休みが少ない業界」というイメージを払拭するため、週休2日+長期休暇を整備するケースが増加中です。
大手チェーンの休暇改善への取り組み
大手飲食チェーンでは、スタッフの定着率を高めるために以下の取り組みが進んでいます。
- 連休取得を義務化
- 有給休暇の計画的付与制度
- 残業時間の削減を目的としたオペレーション改善
このように、業界全体として「休める職場づくり」が少しずつ広がっているのです。
飲食店に「休みがない」という考えは働き方と職場選びで変わる

飲食店は「休めない業界」というイメージがありますが、実際には職場や働き方で大きく変わります。
シフト管理や人員体制が整った店ならしっかり休めますし、休暇制度を整える企業も増えており、働き方改革は進行中です。
つまり「休めない」は業界全体の絶対的な特徴ではなく、職場による差が大きいのです。
飲食業界で長く働きたいなら、「休みを大切にできる環境」を選ぶことが最重要といえるでしょう。