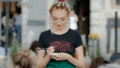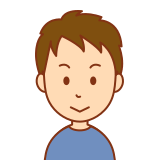
飲食店って長時間労働は当たり前っていう空気があるよね?
それって法律的には問題ないのかな?
飲食店で働いていて
「この働き方って本当に法律的に大丈夫?」
と感じたことはありませんか?
飲食店において、長時間労働や休憩が満足に取れない現場というのは、多々見受けられます。
それなのに、この手に関する法律や制度については、名前だけ聞いてもよく分からないなんてことも。
この記事では、「飲食店の労働時間」について、法律の基本から職場での改善方法、相談先まで丁寧に解説します。
自分の働き方が正しいのか、見直すきっかけになれば幸いです。
この記事で分かることは以下の通りです。
わたくし、かーりーは、20年以上、様々な飲食店で働き、その後、他の職種へ転職しました。
その経験や知識をもとに今回のお悩みに応えていきます。
飲食店の労働時間は法律でどう決まっている?

飲食店で働いていて、
「この働き方、本当に大丈夫なのかな?」
と感じたことはありませんか?
実は、労働時間については法律でしっかりとルールが決まっています。
法定労働時間や休憩のルール、シフトの仕組みなどを知ることで、今の働き方が正しいのか、自分を守る手がかりになります。
ここでは、飲食店で働くうえで知っておきたい労働時間に関する法律の基本を、わかりやすく解説していきます。
法定労働時間と所定労働時間の違い
労働時間には「法定労働時間」と「所定労働時間」という2つの言葉があります。
- 法定労働時間→労働基準法で決められている上限時間のこと。基本は1日8時間・週40時間。
- 所定労働時間→会社やお店が就業規則などで定めた働く時間のこと。
たとえば「うちは1日7時間勤務です」という場合、その7時間が所定労働時間になります。
この違いを知っておくと、残業が発生したかどうかの判断がしやすくなります。
1日8時間・週40時間の原則とは
法律では、1日8時間・週40時間を超えて働かせることを原則として禁止しています。
つまり、週5日働く場合、1日8時間が限度になります。
これを超えて働く場合には、会社と労働者代表との間で「36(サブロク)協定」という書面を交わし、役所に届け出る必要があります。
このルールを守っていないのに、残業をさせている職場は違法の可能性があります。
「これって普通なのかな?」と疑問を感じたら、法律の基準を思い出してみてください。
労働時間に含まれる業務・含まれない業務
意外と見落としがちなのが、「どこまでが労働時間か」という点です。
お店によっては、開店前の仕込みや閉店後の片付け、制服への着替えなどが勤務時間にカウントされないことがあります。
しかし、これらが業務命令として行われている場合、労働時間として扱うのが原則です。
たとえば、
「10時開店だけど、9時には来て仕込みを始めて」
と言われたら、その9時からが労働時間に含まれます。
曖昧になっている部分があれば、しっかり確認しておくことが大切です。
6時間勤務以上で休憩が必要?その法律ルールとは
休憩にもルールがあります。
労働基準法では、6時間を超えて働く場合は最低45分、8時間を超えると最低1時間の休憩を取らなければなりません。
この休憩は、業務から完全に解放されている時間である必要があります。
たとえば、
「休憩中だけどお客さんが来たら出てね」
と言われるなら、それは休憩とは言えません。
特に飲食店では、混雑時に休憩が削られがちですが、法律上はちゃんと守るべき時間です。
「いつも通しで働いてるけど大丈夫?」
と不安を感じている人は、一度見直してみると良いでしょう。
飲食店の労働時間が長い理由とは?他業界との比較と実態

「飲食店って、なんでこんなに長く働くのが当たり前なの?」
と感じている人は少なくありません。
実際、飲食業は他の業界と比べても労働時間が長くなりやすい特徴があります。
営業時間の長さや業務の多さ、人手不足など、さまざまな理由が絡んでいるからです。
ここでは、なぜ飲食業が長時間労働になりがちなのか、その背景と他業界との違いについて詳しく見ていきましょう。
なぜ飲食店は長時間労働になりやすいのか
飲食業界で働いていると、
「朝から晩までずっと店にいるな…」
と感じることがあります。
理由は、営業時間が長いことに加えて、仕込みや片付けなど開店・閉店作業があるからです。
また、忙しくなるタイミングが日によって違うので、シフト通りに上がれない場合も多々あります。
そして、これにともないピークタイムに人手が足りず、シフト交代がスムーズにいかないことも。
僕の経験でも、ランチ営業後すぐにディナー準備に追われ、休憩がまともに取れない日がよくありました。
こうした構造的な理由が、飲食業を長時間労働にしやすくしているんです。
飲食店の平均労働時間と他業界の違い
飲食業の正社員は、月に200〜250時間働くのが当たり前とされています。
一方、一般的な会社員の平均は月160時間前後ですから、明らかに差があります。
土日祝日が忙しい飲食店では、休みが平日で分散されるため、感覚的にも「休めていない」と感じがちです。
「飲食業の労働時間は長いもの」
と思い込んでしまいやすいですが、他の業界と比べることで異常に気づけることもあります。
自分の働き方が平均より極端に多いなら、一度見直すきっかけになるはずです。
12時間労働は当たり前?現場スタッフのリアルな声
飲食店で、
「12時間働くのが普通」
という空気は、正直まだ根強く残っている所もあります。
僕も、
「開店準備から閉店後の片付けまでいて当然」
と言われたことがあります。
まかないや休憩の時間を抜くと、それでも1日10〜12時間働いているケースが珍しくありません。
拘束時間でで考えると、、ヤバいです。
1日の大半をその店で過ごすってことになってしまいます。
周囲が同じような働き方をしていると、「自分もがんばらなきゃ」と無理してしまう人も多いです。
でも、体力的にも精神的にも長くは続かないので、こうした働き方が当たり前になっている状況は見直すべきだと思います。
飲食店の残業代支給はどうなっているのか?
本来、法定労働時間を超えたら残業代が発生するのがルールです。
ですが、飲食店では「固定残業制」や「みなし残業」が多く、実際の残業時間に見合った支給がされていないケースもあります。
「残業代込みでこの給料」と言われると、それ以上はもらえないと思ってしまいがちです。
でも、実態と給与明細が合っていないなら、労働基準法違反の可能性もあります。
自分の働き方と給料のバランスがおかしいと感じたら、しっかり確認してみましょう。
飲食店の労働時間でよく使われる「変形労働時間制」とは

飲食店では、
「うちは変形労働時間制だから」
と言われることがあります。
これは、忙しい日と暇な日のバランスをとるために、1日の労働時間に柔軟性を持たせる制度です。
一見、便利そうに見えますが、正しく運用されていないと労働者にとって不利になることも。
ここでは、変形労働時間制の仕組みや種類、実際の運用例、注意点などをわかりやすく説明します。
変形労働時間制の種類と特徴(1ヶ月・1年単位など)
変形労働時間制には、1ヶ月単位・1年単位などいくつかのパターンがあります。
たとえば、「週末は10時間、平日は6時間」といった具合に、1日あたりの労働時間を柔軟に調整できます。
ただし、これには事前に就業規則への明記や労使協定の締結が必要です。
単に「うちは変形だから」と口頭で言われるだけでは、制度として成り立ちません。
制度の種類と手続きがきちんと守られているか、確認することが重要です。
飲食店で導入されている理由とメリット・デメリット
変形労働時間制は、忙しさの波がある飲食店にとっては便利な制度です。
ピークの週末に長く働いて、暇な平日に短くすることで、無駄な人件費を減らせます。
従業員にとっても、予定が立てやすくなるというメリットもあります。
一方で、
「長時間労働が当たり前になってしまう」
「実際は調整されていない」
といったデメリットもあります。
制度が悪いわけではなく、運用の仕方次第で良くも悪くもなるんです。
適切に運用されていないケースと違法性のリスク
実際の現場では、「変形労働時間制」を導入していると言いながら、必要な手続きがされていないこともあります。
たとえば、労使協定がなかったり、労働時間の管理がずさんだったりするケースです。
これでは法的に変形労働時間制とは認められず、通常の残業計算が必要になります。
もし「うちは変形だから」と言われていても、労働時間が極端に長いままなら要注意。
少しでも違和感を感じたら、制度の正しい運用がされているか確認するのが大切です。
36協定との関係と注意点
「36協定(サブロクきょうてい)」とは、
法律で定められた労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるために、会社と従業員が結ぶ協定
のことです。
この協定を結んで労働基準監督署に届け出ていないと、会社は原則として残業や休日出勤を命じることができません。
たとえ「変形労働時間制」を導入していても、決められた枠を超えて働かせるなら、36協定が必要です。
よく、
「うちは変形制だから残業代もいらないし、協定もいらない」
と勘違いしている職場もありますが、それは間違い。
変形制で調整できるのは法定時間内だけで、それ以上の労働には36協定と残業代がセットで必要です。
制度を正しく理解し、納得したうえで働けているかどうかが、とても大事です。
飲食店の労働時間を減らすための具体的な改善策

「今の働き方、どうにかならないかな…」
そう感じたら、改善の余地は必ずあります。
飲食店での長時間労働には、業務のムダや人員不足、慣習的な働き方が影響しています。
だからこそ、まずは自分でできることから少しずつ変えていくことが大切です。
この章では、現場で実際に使われている改善策を紹介しながら、より良い働き方へのヒントをお伝えします。
業務効率化で時間を削減する方法
時間を削る一番の近道は「ムダな作業を減らすこと」です。
たとえば、仕込みを外部の業者に委託したり、食材をあらかじめカットされた状態で仕入れたりする工夫があります。
厨房の動線を見直したり、メニュー数を絞ったりするだけでも作業時間はグッと減ります。
「当たり前」になっている作業こそ、見直してみる価値があるんです。
シフトの希望や労働時間を交渉するにはどうする?
「今月も希望休が通らなかった…」そんな悩み、ありませんか?
シフトや労働時間の調整は、我慢せずにちゃんと相談することが大切です。
そのためには、まず希望を具体的に伝えること。
「毎週水曜は家族の予定がある」といった背景を共有すると話が通りやすくなります。
また、繁忙日と被らないように希望を出すなど、店側の状況も理解しながら交渉するのがコツです。
「ただ文句を言う人」にならず、「一緒に解決したい」という姿勢が伝わると、意外と受け入れてもらえるものです。
長時間労働を減らすために取り入れられている工夫
今の飲食業界では、少しずつ「働き方改革」が進んでいます。
たとえば、営業時間を短縮したり、通し営業をやめて中休みを設けたりするお店も増えてきました。
予約システムやセルフオーダー機など、デジタルツールの導入で人手の負担を減らす工夫も広がっています。
「どうせ無理」と思わずに、まずは身近な工夫から見直してみると、未来が変わるかもしれません。
同僚や上司とのコミュニケーションのコツ
働き方を改善するには、職場内の人間関係も大切なカギになります。
日ごろから上司や同僚と信頼関係を築いておけば、シフトの相談や働き方の提案もしやすくなります。
大事なのは、「普段から自分の思いや状況を共有しておくこと」です。
急に「もう無理です」と伝えても、相手は驚いてしまいます。
「最近、体力的にきつくて…」と、軽く相談から始めるだけでも雰囲気は変わります。
しんどい気持ちを我慢しすぎず、早めに言葉にしてみましょう。
飲食店の労働時間が違法かも?相談先と行動のステップ

「これって本当に合法なの?」
と疑問を感じたとき、行動を起こすかどうかで状況は大きく変わります。
飲食業界には、法律を知らずに違法な働き方が続いている職場もまだあります。
ただし、いきなり「違法だ!」と騒ぐのではなく、まずは事実を確認し、冷静に対応することが大切です。
ここでは、違法の判断基準や相談の流れ、証拠の残し方など、具体的なステップを紹介します。
労働基準法違反の具体的な判断基準
労働時間に関して、違法とされるのは、次のようなケースです。
- 法定労働時間を超えて働かせたのに残業代を払わない
- 休憩を取らせない
- 休日が極端に少ない
また、
「36協定がないのに残業をさせている」
「シフトと実際の労働時間が違う」
といった状態も要注意です。
「なんとなくキツい」ではなく、法律で定められた基準と照らし合わせて確認することで、違法性があるかどうかが見えてきます。
もし基準を明らかに下回っていたら、それは我慢しなくていいラインです。
労働基準監督署への相談方法と流れ
違法の疑いがある場合は、労働基準監督署に相談するのが正しいルートです。
電話・窓口・WEBフォームなどで受け付けており、匿名でも相談できます。
相談では、「勤務時間の記録」「給与明細」「シフト表」など具体的な資料があると話がスムーズです。
調査が必要と判断された場合は、実際に会社へ立ち入り調査が入ることもあります。
「こんなことで大丈夫かな…」と迷ってたらまずは一度相談してみることが大事です。
記録(タイムカード・LINE・シフト表)の取り方と保管方法
働いた時間を証明するためには、客観的な記録が欠かせません。
タイムカードがあればベストですが、ない場合はスマホのメモやLINEでのやりとり、レジのログ、監視カメラ映像なども証拠になります。
出勤・退勤時間を日付ごとにメモしておくだけでも、十分な資料になります。
これらの記録は、突然削除されたり紛失したりしないように、自分でコピーやスクショをとって保管しておくと安心です。
状況によっては転職や退職を考えるべきケースも
「何度言っても改善されない」
「身体や心がもう限界」
という場合、環境を変えることも選択肢のひとつです。
飲食業界すべてがブラックなわけではありません。
労働時間をしっかり守っている店も、最近は増えてきています。
僕も転職したことで、体力的にも精神的にも余裕ができました。
今の職場で無理をし続けるより、自分に合った環境を探した方が、長く飲食の仕事を続けられることもあるんです。
飲食店の労働時間に関するよくある質問

ここでは、飲食業で働く中でよく聞かれる疑問にお答えします。
「アルバイトはどこまで働いていい?」
「休憩が取れないのは普通?」
など、意外と知られていない労働時間に関するルールはたくさんあります。
法律を知ることで、「自分の働き方って正しいのかな?」という不安を減らせるはず。
今の職場で感じるモヤモヤを、スッキリ解消するヒントになればうれしいです。
アルバイトも1日8時間を超えたら違法?
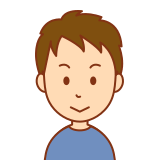
アルバイトでも8時間超えたらダメだよね?
学生の場合はどうだろう?
アルバイトでも、基本的には1日8時間・週40時間を超えて働かせるにはルールがあります。
会社が「36協定」を結び、残業の手当をしっかり支払っていれば問題ありません。
ただし、学生など短時間契約の人を長く働かせておきながら残業代を払わないのは完全にNG。
アルバイトでも「労働者」であることは変わりません。
正しい知識を持って、自分を守りましょう。
休憩時間が取れない日はどうしたらいい?
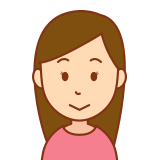
飲食店っていつ忙しくなるか分からない。
だからまともに休憩が取れなかったりするんだよね。
この場合どうしたらいいんだろ?
6時間以上働いたら最低45分、8時間以上なら1時間の休憩を取らせるのが法律です。
これが守られていない場合は、まずは上司に「休憩が取れていません」と伝えるのが第一歩。
それでも改善されなければ、メモを取ったうえで労基署への相談も検討しましょう。
「忙しいから仕方ない」は理由になりません。
体を休める時間は、働くうえで当然の権利です。
飲食業界で労働時間が短い職場を見つけるには?
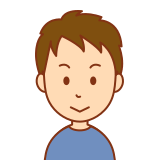
飲食店だけど、労働時間が短い職場はないのかな?
労働時間が短い職場を探すには、まず求人情報の「勤務時間」と「残業」の項目をチェックしましょう。
「固定シフト制」や「分業が進んでいる職場」は、比較的労働時間が安定しやすい傾向があります。
実際に働いている人の口コミサイトやSNSの情報も参考になります。
僕は転職前、面接のときに「1日の平均労働時間」を聞いて確認していました。
勇気はいりますが、働き始めてから後悔しないためにも、気になる点は事前にしっかり聞くことが大切です。
飲食店の労働時間を見直して、無理なく働ける環境へ

飲食業界には、やりがいも魅力もたくさんあります。
でも、無理をして働き続けることがすべてではありません。
長すぎる労働時間や取れない休憩が当たり前になっているなら、一度立ち止まって自分の働き方を見直すことが大切です。
制度やルールを知ることで、「仕方ない」と諦めずに行動を起こすことができます。
ここで紹介した内容が、その第一歩になれば嬉しいです。